| 「四万十の森」の原風景 |
澤良木庄一 |

|
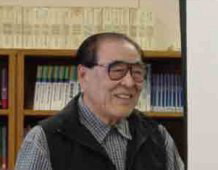
<講演:四万十川森林植生の特徴と価値
(H.13.11.25:西土佐村)> |
|
「四万十の森」の原風景<原生林>は、どのようなものであったのか?日本における自然植生の広がりは4つに大別されます。そのうち四国には次の3つの植生域があるとされています。
| 1. |
シイ、カシ、タブノキなどの生育している常緑広葉樹林帯 |
| 2. |
四国山地の一部でブナの林がある夏緑広葉樹林帯 |
| 3. |
石鎚山系や剣山系の一部でシコクシラベ林に代表される亜高山針葉樹林帯 |
四万十川源流の不入山の標高が1,336mで、2,000m級の山々に代表される亜高山針葉樹林帯には属しません。不入山では山頂近くまでブナ林が続いています。高木層はブナをはじめ、ツガ、ヒメシャラなどが林冠をつくり、下層は背丈以上もあるスズタケに覆われています。ブナ林の下層植生にササ類が生じるのは、日本のブナ林の特徴で、不入山の原生林(夏緑広葉樹林)であるブナ林は、このうち太平洋側のブナ林のタイプであるブナ・スズタケ群団に属する森林です。
その源流域の森林から190km余り下った、中村市入田の川原にヤナギ林が帯状に分布しています。樹高は1mから10mですが、約200mの幅で堤防に沿って1.5kmほど続いています。ヤナギ林中央部には縄文後期から弥生前期への移行期の遺跡「入田遺跡」があります。平成6年、中村市山路の四万十川の河床から発掘されたアカガシ亜属の巨木は、1400年前の洪水時にこの付近から流されてきたと想像されています。
2千年前にはこのあたり一帯はうっそうと茂ったタブ・シイ・カシなどの原生林(常緑広葉樹林)で覆れ、その中で人間の生活が営まれていたことが想像されています。人間が定住し、稲作を始めるようになると、そのような林はどんどん切り開かれ、長い年月をかけ、今日の私たちの生活域となったのです。今日の人間の生活域近くでは、入田のヤナギ林のように水辺という環境が育てた森林はありますが、原生林はほとんど見ることができなくなっています。四万十川の流域一帯はかつて常緑広葉樹林で覆われ、源流域のブナ林に代表される夏緑広葉樹林とともに、それが、「四万十の森」の原風景<原生林>であったと考えられます。
「四万十の森」の原風景を構成する自然植生は、生活域はもとより、分水嶺近くの奥山まで開発がすすみ、破壊もしくは変形され続けてきました。しかし、植生の豊な四万十川の流域には、往時をしのぶことができる森林がまだまだ、あちこちに残っています。そのような森林は人類の世界遺産です。もうこれ以上、開発をすることは、やめなければなりません。
また、2千年近くにわたって開発され続けてきた森林は、もし、人間がいっさい消えてしまったら、おそらく長い年月をかけ、自然がもとあった原生林の姿に復元するだろうと推定されています。しかし、地球上に人間がいる限り、森林が人間と共生する限り、早急な原生林への復元は非常に難しく、また、森林復元には多くの時間を必要とする問題です。しかし、だからといって、何もしないでいる事は許されません。森林復元に向けた人間のサポートがいま必要な時なのです。
地球にとっても、あるいは人間にとっても「好ましくない状態の森林」があるとしたら、誰にとっても「好ましい状態の森林」、「四万十の森としてふさわしい森林」に誘導することが、長きに渡って森林を開発してきた人間のせめてもの償いであり、また、21世紀を生きる後世の人々に対して、果たしておかなければならない責務でもある、と考えます。 |
 話・輪・和<リレーエッセー> 話・輪・和<リレーエッセー>
 |
| 次回は、宿毛市で医院を開業している崎村泰斗氏です。宿毛市の出身で子どもの頃、四万十川の赤鉄橋まで自転車で泳ぎに行っていたそうで、その思い出話です。「小谷貞広写真百選・その3」は「赤鉄橋下のにぎわい」ですが、ちょうどその頃のエピソードです。また、崎村氏はかって純白のユニホーム、全力疾走で有名な名門「土佐高校」の応援団長でした。著書に昭和50年夏、51年春、サイクルヒットの玉川を擁し甲子園に出場した時の青春感涙手記『アルプス席の全力疾走』があります。
|