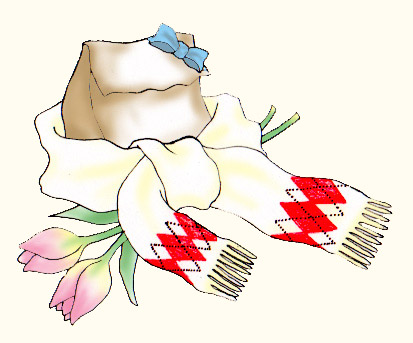S p r i n g h a s c o m e ? 賑やかな夜の街。その片隅に居るような気持ちで、ぽつんと大原はガードレールに座っていた。
「…っくしょっ。」
今夜ここでの三度目のくしゃみに、思わず呟く。
「春なのに、寒い…。まだ春じゃないのか…。」
なんだ、夜は寒いじゃないか。3月って春って感じだけど、夜はまだマフラー欲しいよなー。
そんなことを思いながら、大原はある居酒屋の裏口が見える所で、ガードレールに座ったまま動かない。もう、一時間近くになるだろうか。大原はその裏口から、ユウコが出て来るのを待っていた。
今日は3月14日。ユウコに、ホワイトデーのプレゼントを渡すために。ユウコ。この居酒屋でアルバイトをしている女の子。その他の事は何も知らない。バイトと分かるのは店内のエプロンの色分けで。名前も、店内で呼ばれているのを聞いて下の名前だけ知った。
大原は、彼女に恋をした。
「安くて食い物もウマイから」と仕事仲間に誘われて、ある日大原はこの居酒屋へ来た。そこへ、おしぼりを持って来たのが、彼女だった。
「あ。」
彼女は大原の顔を見ると一瞬目を丸くした。
それを見て大原は、騒がれるのか、笑われるのか、好奇心いっぱいの目で見られてしまうのか…と身構えて俯いた。野猿で顔が知られてから、正直、それが嬉しくもあり、少し悲しくもあった。
けれど、すぐに彼女は明るい声で
「いらっしゃいませ。」
と言うと、テーブルの脇のお品書きを広げ、おしぼりを並べ始めた。
そして、最後に大原の前におしぼりを置きながら、小さな声で、
「いつも見てます。応援してます。」
とだけ言った。大原は顔を上げた。彼女は大原と目を合わせて、にっこりと微笑んでいた。その笑顔に、大原は、頬が赤くなった気がした。
それ以来、大原はそこの常連客になった。
大原はなるべく、同じ席に座るようにした。いつも彼女が、おしぼりを持って来た。大原は声もかけられずに、その後ろ姿を見つめるだけだった。
今さら、中学生みたいな片思い…?
自分でもそう思いながら、でも、彼女と目が合うだけでドキドキしていた。
こういうとこで働くの、大変なのに…疲れた顔も見せないで、いつも元気に笑ってるよな。オレのコト分かってても、普通に接してくれて…。人を嫌な気持ちにさせない、いいコだな。でも一度だけ、彼女の笑顔が曇ったことがあった。
無意識に彼女を目で追っていた大原は、店の隅の方で酔っ払い客にからまれている彼女に気付いた。
あっ。時々、あるんだろうな、こういうこと…。どうしよう…助けてあげたいけど…返って騒がれたら…ケンカなんか出来ないし…。
大原は食べる手も止まり、眉間に皺を寄せて首を伸ばして見つめた。ちょうど柱の影になるような位置で、客も強引に彼女の腕を引っ張る。最初は無難にかわそうとしていた彼女も、さすがに困り果てているようだった。
あの野郎〜…。
握った拳に力が入る。けれどやっぱり大原は立ち上がれずにいた。情けなく睨むだけのその視線の先で、客は彼女の腰に手をまわした。彼女の顔が歪む。
大原は、テーブルを叩くようにして席を立った。
「〜うわぁ〜っとぉ〜!あ、痛ぇ〜…。」
これ以上ないぐらいの千鳥足で酔っ払いを演じて、大原は彼女と客の間に、思いっきり、転んだ。一緒に倒れてしまわないように、彼女をかばいながら。
「あ〜、すいませ〜ん、トイレってどっちですかねぇ〜?」
大原は倒れたまま、酔っ払い客に負けないバカ笑いの顔でそう言いながら、彼女に向かって手を伸ばした。
「だ、大丈夫ですか?」
彼女に腕を引っ張ってもらいながら、起き上がる。
「すいませ〜ん、どうも〜。」
大原がちらりと客を見ると、苦虫を噛み潰したような顔で睨まれたが、それ以上は何もなかった。彼女に連れられて、トイレへと向かう。
「ごめんね、大丈夫だから。」
心配する彼女に、大原は素に戻ってそう告げると、逃げるようにトイレに入った。
ああ〜もぉ〜、ビビったぁ〜!何にもされなくて良かったぁ〜。だけど彼女の笑顔はオレが、…なんとか、守った…よな?出来れば、もうちょっとカッコよく守りたかったけど…。まぁ、いいや。
大原は大きく安堵の溜め息をついて、ついでに用も足して、トイレを出た。
視線を感じて顔を向けると、厨房の入り口でお盆を抱えた彼女が、まだ心配そうな顔でこっちを見ている。大原は照れ笑いを浮かべて、ひょこっと頭を下げた。彼女は、深く頭を下げた。そして、やっと笑顔に戻る。その唇は、
「ありがとうございます。」
と、言っていた。大原はますます照れて、頭を掻きながら席に戻った。そんなことがあった後の、バレンタインデー。職場では成井が彼女からチョコを貰い、成井にも自分にも、ファンからのプレゼントが届いていた。
大原は少しだけ期待して、その居酒屋に行った。
義理でもいいから、欲しいなぁ…。ユウコちゃんから、バレンタインのチョコレート。この前のお礼です、とか言って。
想像にニヤつきながら、大原は店に入った。いつもの席に座る。いつものように、彼女がおしぼりを持って来た。
「この前は、本当にありがとうございました。」
「あ、うん。」
それだけだった。想像を膨らませたようなことは、何も起こらなかった。
…そんなもんだよな…。ふっ…。
大原は遠い目をして笑った。店を出るその背中は、丸くうなだれていた。そして先日の事だ。大原は事務所で、成井の荷物の中に「WHITE DAY」とリボンが掛けられた包みを見つけた。
ああ、そっか…もうすぐホワイトデーか…。成井さん、しっかりしてるなー、もう用意してる。オレはそんな相手もいないけどさ。お返しかぁ…、したかった人は、いるけどさ…。
ふと、大原は閃いた…と、本人は思った。
お返しじゃなくても、あげてもイイかな…?バレンタインデーが女の子からだったら、ホワイトデーに男からプレゼントしてもいいんじゃないかな?
彼女に声をかける口実が思い付かずに、今まで過ごしてきた大原だった。彼女をいいコだなと思う度に、軽くナンパする勇気がなくなった。自分でも笑ってしまうほど、純情な恋心を抱いている。
「成井さん、ホワイトデー、何あげるんですか?」
隣に座った成井に聞いてみた。いきなりの質問に、ただでさえその手の話の苦手な成井は、少し戸惑いながらも答える。
「何って…普通に…マシュマロと、プレゼント。」
「マシュマロとプレゼント…が、普通なんですか?プレゼントって?」
「普通って言うか…。お菓子は、マシュマロとかキャンディーとかクッキーとかだろ?その中じゃ、あいつがマシュマロが好きって言うから。プレゼントは、やっぱ、義理じゃなくて彼女だからな。ペンダントを…。」
「ペンダントか…。ああ、そっか、本命にはお菓子プラス、プレゼント…。」
そういやテレビや雑誌で毎年言ってるよなぁと、大原は今さら思い出す。その隣で成井が、何か気付いたように目を輝かせて聞いてきた。
「何、大原、ホワイトデーに返す本命が出来たのか?」
「いえ、返したかったけどね、その前に、貰えなかったっす。」
「なーんだ。」
呆れて立ち上がる成井も見ずに、大原は明日のスケジュール表を確認する。明日は朝が早い分、終わるのも早かった。
翌日、大原は仕事帰りにデパートへ行った。彼女へのホワイトデーのプレゼントを買うために。…バレンタインのお返しではないプレゼントを…。
だがそこで山のようなお菓子を眺めて、大原は困惑した。
オレ、ユウコちゃんのこと、何にも知らないんだよなぁ…。何あげたらいいのかわかんねぇや…。
小さく溜め息をつくと、大原は顔を上げて自分に言い聞かせる。
オレがいいと思ったものをあげるしか、ないよな。
大原は、自分の好きな、バタークッキーを選んだ。そして、プレゼントコーナーへと向かう。が、そこでも並べられた華やかなプレゼントの数々を前にして、今度は大きく溜め息をついた。給料日前の大原の目に、値札が滲みる。
気持ちは値段じゃない!
そう言い聞かせて顔を上げた大原の視界の隅に、小さく綺麗な赤い色が映った。「冬物最終セール」と書かれたワゴンに積まれた、マフラーだった。その赤い模様のマフラーを引っ張り出す。柔らかな白い色に赤いアーガイルの模様の入った、可愛らしいマフラー。
彼女にピッタリだ。
大原は嬉しそうに微笑んだ。一応値段も確認して、迷わずそれをレジへ持って行く。
「プレゼントですか?」
「はいっ。」
少し照れながら小さな声で、でも、はっきりと大原は頷いた。
キレイに包装されたクッキーとマフラーが入った紙袋を下げて、大原は意気揚々と、売り場を後に…するはずだった。しかし、大原の耳に、二人の女性の会話が入ってきた。
「あ、マフラー、安くなってる。」
「でもさ、もう3月だし、寒くてもマフラーなんか出来ないよねー。」
「うんー、来年は、また新作が欲しくなるだろうしねー。」
大原は思わず立ち止まる。
…え?そうなの…?
手に下げた紙袋に目を落とした。
何これ?って、思われる?…いや、でもだからって他には…。それに、オレはこれが彼女に似合うと思うし、そんな、3月はもうマフラー出来なくたって、また冬は来るんだし、彼女なら大事に使ってくれる…と、思いたい…。
たった1時間の内に、自分に言い聞かせることで頭がいっぱいになった。大原は軽い目眩を覚えながらも、紙袋をしっかりと握って、帰って行った。「っくしょいっ。」
そんなわけでホワイトデーの今日、大原は四度目のくしゃみをしながらも、じっと待ち続けていた。
店の中で渡そうかとも思ったが、彼女は仕事中だし、迷惑になるといけないからやめた。外で彼女の仕事の終わりを待ち始めて、大原はまた一つ、彼女のバイトのスケジュールも知らない、ということに気付く。
これ、閉店まで待つとなると、ちょっとキツイなぁ…。
時計を確認すると、9時半が来ようとしていた。
その時、裏口が開いた。
ユウコちゃんだ!
大原は弾かれたようにガードレールから飛び下りた。彼女もそれに気付いたらしく、こちらを向いた。彼女と、大原の目が合う。
「あ。」
「こんばんは。」
二人同時だった。彼女は、最初に合った時と同じように目を丸くして声をあげた。大原は、ドキドキする左胸とプレゼントの入ったショルダーバッグをぎゅっと掴んで、挨拶をした。
「あ、えっと、今日は、もう仕事終わり?」
大原が駆け寄って、歩道の端で二人は向かい合う。くっきりとした二重の目を大きく開いた彼女に見上げられて、大原はしどろもどろになりそうだった。
そっか、店の中じゃ、オレが見上げてばっかりだったもんな。背が高く見えたけど、オレと並ぶとこんなもんなんだ…。きれいな目…。
そんなことを考える大原の前で、彼女はいつもの笑顔で答える。
「あ、はい。今日はちょっと用事があって、早めに…。大原さんこそ、どうしたんですか?」
「用事が…?じゃ、時間ないんだ。あ、あのね、オレ、ユウコちゃんに渡したいものがあって…。」
そう言いながら、大原は慌ててバッグを開ける。自分がつい、相手の名前を、いつも心の中で呼んでいるまま口にしたことに気付かずに。そして、それを聞いて彼女がまた大きくまばたきしたことにも、もちろん気付かずに。
「これっ。ホワイトデーのプレゼントなんだけど、貰ってください。」
「…え?」
目の前に差し出された、水色のリボンが掛かった包みを見て、彼女は当然の反応をした。
「あの…でも、私、バレンタインにプレゼント、してないですけど…。」
戸惑って見つめる彼女に、大原は、昨夜必死で考えて用意したセリフを言った。
「うん。でも、オレはいつもキミから笑顔を貰ってるから。これ、オレの気持ちだから、受け取って欲しいんだ。」
顔を赤くしながら棒読みで、でも力を入れてそんなことを言う大原を、しばらく彼女はぽかんと見つめていた。そして、ゆっくりと顔がほころんでゆく。彼女は、顔を崩して笑った。
…やっぱ、セリフがクサかったかな?呆れちゃって笑われてるのかな、オレ。でも…それでもいいや…。今まで見た中で、とびきりの笑顔だ…。
そう思いながら、大原も照れてどうしようもなくて、えへへっと笑った。
けれど、大原のその思いは、違っていた。彼女が口を開く。
「私が笑顔なのはね、大原さんが、笑顔だから。疲れた顔でお店に入って来ても、いつも、私達にも優しく接してくれて、一緒にいる人にも気を使ってて、美味しそうに、食べて、飲んで…。そんな大原さん見てるから、笑顔なんです、きっと。私。」
彼女は嬉しかった。大原のその差し出された気持ちが嬉しくて笑っていた。
うっすらと滲みそうな涙を指で拭い、彼女は、大原が差し出した包みを、そっと両手で受け取った。
「ありがとうございます。」
彼女の言葉のすべてを理解するにはもう少し時間が必要だったが、大原は、プレゼントを受け取ってくれたところで、考える力を無くした。
「あ…良かった。受け取ってもらえて…。」
「開けてもいいですか?」
「あ、うん。」
つい頷いてから、大原は思い出して慌てて付け加える。
「あ、あの、オレ、キミの事よく知らなくて、好みとかわかんなくて、オレの好みで買ったから、気に入ってもらえるかどうかはわかんないんだけど…、」
「可愛いアーガイル!マフラーだぁ。」
言い終わるより先に、彼女の手にプレゼントの中身が握られた。
「私、アーガイル模様、好きなんですよ。バタークッキーも。すごい!じゃ、大原さんと好みが合うんですねっ。」
はしゃぐように言う彼女にホッとして、大原は続きを言った。
「マフラーなんて、もう、しないかもしれないけど、でも良かったら、また今年の冬が来たら、使ってもらえたらと思って…。」
『また今年の冬が来たら』…自分が言ったその言葉に込められる意味に気付かない大原は、零れるような瞳をした彼女に少し驚いていた。
彼女は、くるりと首にマフラーを回して、微笑んで答える。
「はい。また、今年の冬も…。…来年のバレンタインデーは、私が大原さんに、マフラー編みますね。」
彼女からその言葉を聞いて、やっと、大原は胸の辺りがあたたかくなるのを感じた。
…あれ…?これって…。
「あっ!いけない!」
突然彼女が声をあげて腕時計を見た。
「大原さん、付き合ってください!」
いきなりそう迫られて、大原はだらしない照れ笑いを浮かべる。
「うん。付き合おう…。」
「走ってください!お店閉まっちゃうー。」
「えっ?走…?ああ、そっか、用事があるって言ってたよね。」
走り出した彼女を、自分の勘違いを戒めながら追い掛ける。自分が渡したプレゼントを握りしめたまま走る彼女に追い付いて、大原はやっと聞いた。
「あの、オレ、キミの事まだ何にも知らなくて。…名前は?」
「ナガハラです。ナガは、永遠の永。ハラは、原っぱの原。ユウは、優しい。コは、子供の子。永原優子です。」
少しだけ息を切らしながら、明るい声で優子は答える。
「永原優子…。いい名前だね。優子ちゃんか。」
「えー?普通ですよー。あと、優子でいいです。」
クスクス笑いながら、優子はちらっと大原を見て言った。
「でも、いい名前だよ。優子ちゃんの名前だから。」
優子は走っているせいではなく、大原の言葉に頬が熱くなった。大原は平気な顔で、目を細めて頷いている。大原は…思ったままを口にして、その自分の言葉には鈍感なのかもしれない…。
「で、オレ、聞きたいことはいっぱいあるんだけどさ…。まずは、今、どこに走ってってるの?」
「あそこ。あの、CD屋さんです。10時閉店なの。」
優子が指差した、もう少し向こうの歩道橋を渡った所に、確かにそれらしい明かりが見えていた。
「あ、そうなんだ。で、こんな走ってまで、今日買いたいのは、何?」
その質問に、思わず優子は走りながらも大原の方に顔を向けた。
「えぇ?大原さーん、野猿ですよー。今日アルバム発売じゃないですか!」
「あ、そうだよね。え?あ、買ってくれるの?ありがとう!」
驚いて思わず立ち止まってしまった大原は、また、追いかけて優子と並ぶ。
「今日、ちょうどお給料日だから、それで買おうと思って、早めに帰らせてもらったんです。バイトだってね…」
大原が隣に並ぶのを待って、優子は続けた。少し息が荒くなっている。
「あ、あの、無理して話さなくていいから。荷物、オレが持とうか?」
気を使う大原に、優子はちょっと立ち止まった。
「ううん、大丈夫。バイトもね、野猿のためなんです。今、大学生で、一人暮らしだから、お金あんまりなくって。でも、CDは全部買いたいし、コンサートも最後だから、名古屋とか、追加になった最終日も行くから。」
そこまで言うと、優子はまた走り出した。
大原は、感激でぼんやりしながら、つられて走り出す。
そんなにファンだったのか…。そのために、あんな大変なバイトしてくれてたのか…。
「あの、ありがとう。そんなに野猿好きだったんだ。わかんなかったよ。最初に『応援してます』って言ってくれたのもさ、気を使ってくれたのかと思った。いや、すごく、嬉しかったんだけどね、それが。」
「それだけ言うのが精一杯だったんですっ。バレンタインデーだって…。」
隣に居る大原に、今もそれだけ言うのが精一杯のように、優子は怒ったような恥ずかしそうな声で言った。でも、大原が首を伸ばしてその顔を覗き込むと、やっぱり笑っていた。
「そっ…か。」
…そーゆーもんなのか…。で、『バレンタインデーだって』…何だろう…?
相変わらず分かっていない大原は、いつものように、素朴な質問をした。
「あ、ねぇ、野猿のさ、誰のファンなの?」
一瞬の沈黙の後、たまりかねた優子が立ち止まった。
「…もうダメッ。階段走るのはキツーイ!」
これくらいは気付いて欲しいのに、でも、今更それを聞いてくるのが大原だから。大原に背を向けて歩道橋の手すりに掴まって、優子は声を立てずに笑った。
「大丈夫?優子ちゃん。あ、ごめん、オレ、いっぱい喋らせちゃって。知りたいことあり過ぎて…でも今全部なんて、ムリだよね。これからゆっくり、一つずつ…。ね、やっぱ荷物持つよ。はい。マフラー、暑くない?」
大原は、優子の揺れる背中に心配そうに焦って声を掛けて、その背中の小さなリュックを持ち上げた。
やっと息を落ち着けて、リュックから腕を抜きながら優子が振り向く。
「ありがとうございます。これは、私が持ちますから。」
顔を上気させてもマフラーを取らず、胸の前にクッキーを持って、大原を見上げる。優子の仕草が可愛くて、大原は、
…もしかして…オレ…?
と、思いかけていた、さっきの質問を忘れた。
二人で息を切らしながらの会話も、もうすぐ終わりそうだった。あとは、歩道橋を降りるだけ。大原も、優子と同じ笑顔になっていた。
「コンサート、最終日も、来てくれるんだ。」
「うん。絶対、何があっても行きます。」
「じゃ、ステージの上から見つけて、手ぇ振るよ。」
「あはは、そんなの無理ですよぉ。席、遠いんだもん。」
「あ、そっか…。でも…オレ、優子に、手、振るよ。」END.
Back